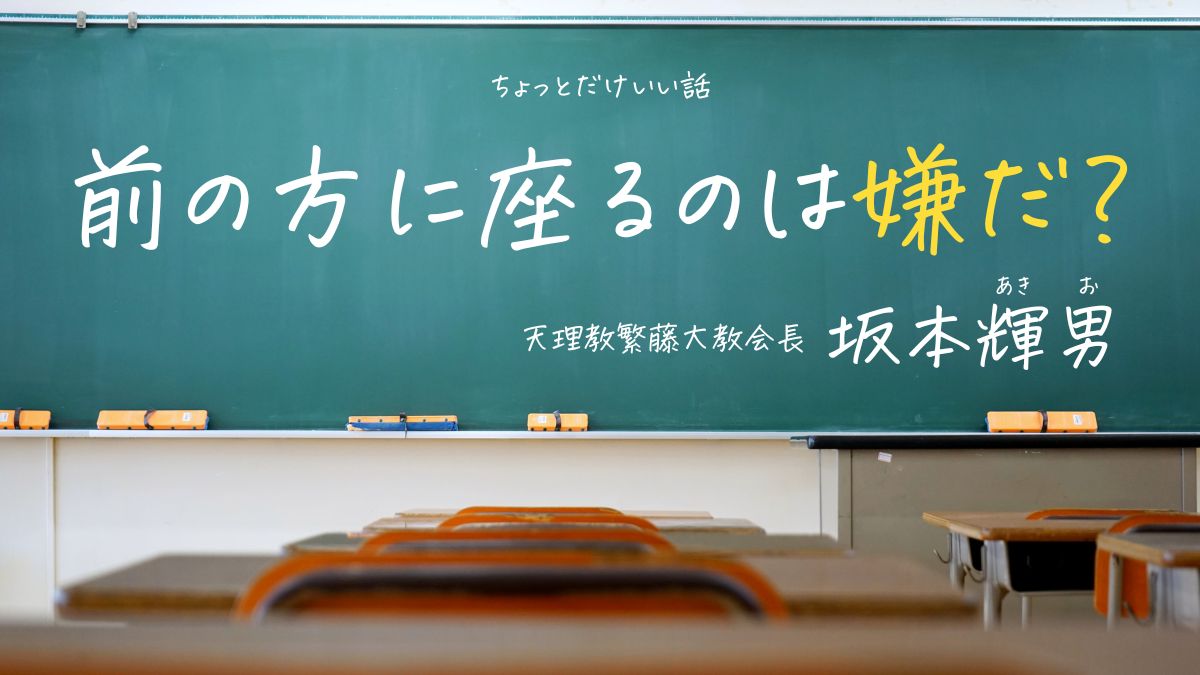最初に質問をしたい。あなたは今、授業が始まる前の教室に着いたところだ。次の授業は教室のどこに座るのも自由。そして、まだ教室には誰もいない。さて、あなたは教室のどこに座るだろうか?
遠慮か? それとも自己防衛か?
まず私の答えを言おう。
それは窓側の後ろあたりだ。前の方に座って質問を当てられるのは嫌だし、何より目立ちたくない。後ろの方なら、内職(こっそり違う教科の勉強をすること)ができるし、スマホも触れる。
少々居眠りしたってバレにくいし、窓の外の景色を眺めてぼーっとするのもいい。もっともHappistの読者の皆さんが、過去の私のように不真面目な学生でないことを願うばかりだが、実際このことに共感してくれる方も少なくないはずだ。
不真面目なのは別として、前の方に座るのを避けるこの問題については、世代や性別による違いがあまりないと感じる。例えば、うちの教会でも同じようなことが起こる。月次祭の日、神殿内のどこが初めに埋まるかといえば、両端か後ろの方だ。参拝者の多いときは、神殿前方にはまだ空きがあるにもかかわらず、廊下に座る人が出てくることもある。
授業の席にしろ、神殿の座る場所にしろ、そういう現象が起こるのは日本人的な「遠慮」からなのか。それとも見えない同調圧力の中で、目立ちたくないという自己防衛が働くからなのだろうか。

最前列は悲しい? それともうれしい?
例えばこれが、好きな人気アイドルのコンサートだったらどうだろう。高倍率の狭き門をくぐり抜け、勝ち取ったチケットはなんと最前列。推しからウインクでもされようもんなら、天にも昇る心地になるはずだ。
コンサートと授業は別物だろうか。いや、いつもは後ろに座る人も、単位を落としそうで必死になっていたり、夢中になれるような授業だったら、最前列に座ることもあるだろう。教室や神殿の前方スペースが空いてしまうのは、日本人の群集心理ゆえもあるだろうが、それを凌駕する熱量や真剣さがあれば、話は別ではないだろうか。
最前列という文脈であれば、毎月おぢばの月次祭を最前列で参拝している人たちがいる。私の母もその一人だ。一番前で参拝するには、早めに神殿に行かないといけない。現に、母は朝づとめのずっと前から神殿に向かう。夏の暑い日も、冬の凍える寒さの日もだ。子どもの頃はなぜそんなことをするのか理解できなかったが、今なら分かる。感謝の気持ちや誰かのたすかりを願って真剣に祈る心、そんな熱がしっかりと込められているのだ。
力を入れる、心を込める
教祖が力比べをなされたという逸話がいくつもある。力自慢の男性がご高齢の教祖と力比べをすると、太刀打ちができなかったという逸話だ。そのとき、教祖はこうおっしゃった。
そっちで力をゆるめたら、神も力をゆるめる。そっちで力を入れたら、神も力を入れるのやで。この事は、今だけの事やない程に。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』174「そっちで力をゆるめたら」
もちろん神殿前方に座るのと、後ろに座るのでご守護が変わるということではないし、周りの参拝者への配慮は必要だ。ただし、一ついえるのは、親神様は私たちの心を受け取ってくださる。
「周りの目を気にして」とか、「まぁこれくらいでいいだろう」といった姿勢か。それとも祈り、おつとめに対しての真剣さ、熱い思いがその姿勢にまで込められているのか。「神も力を入れる」のはどちらか明白だろう。前のめりな姿勢は決して恥ずべきことではないのだ。
さて、次に参拝するとき、あなたはどこに座るだろう?