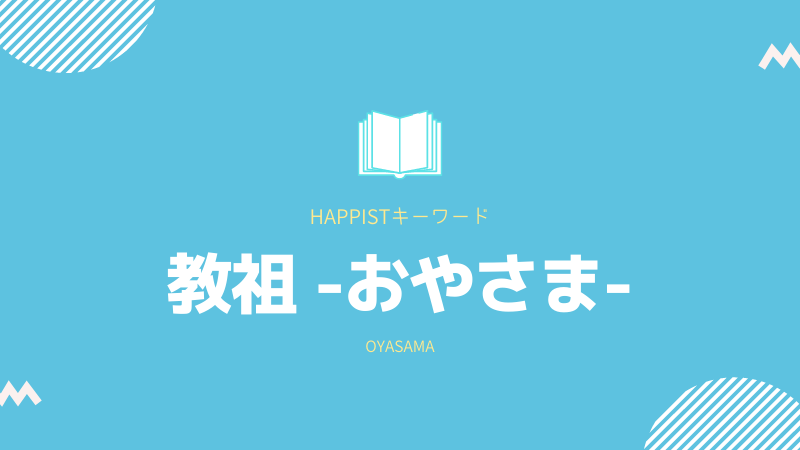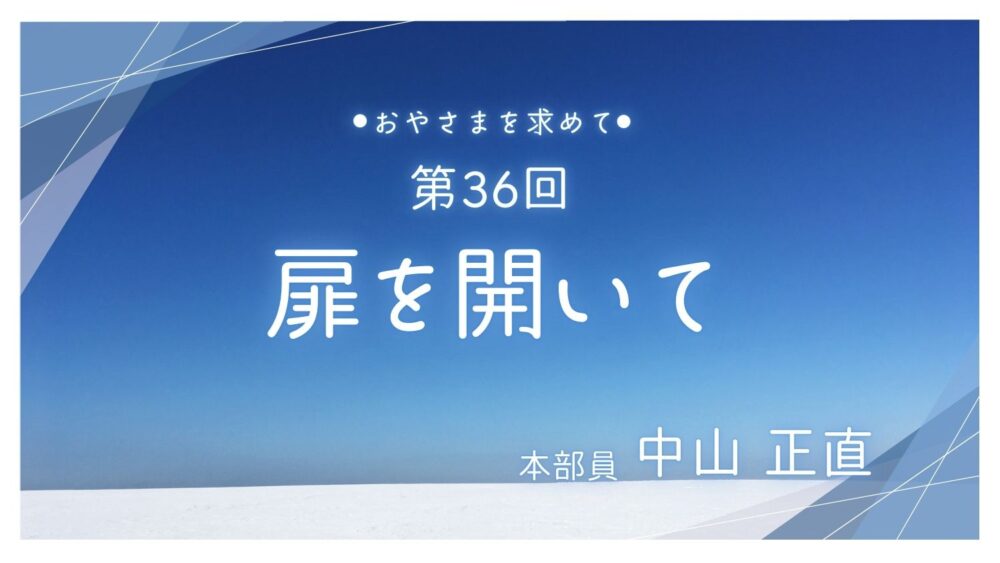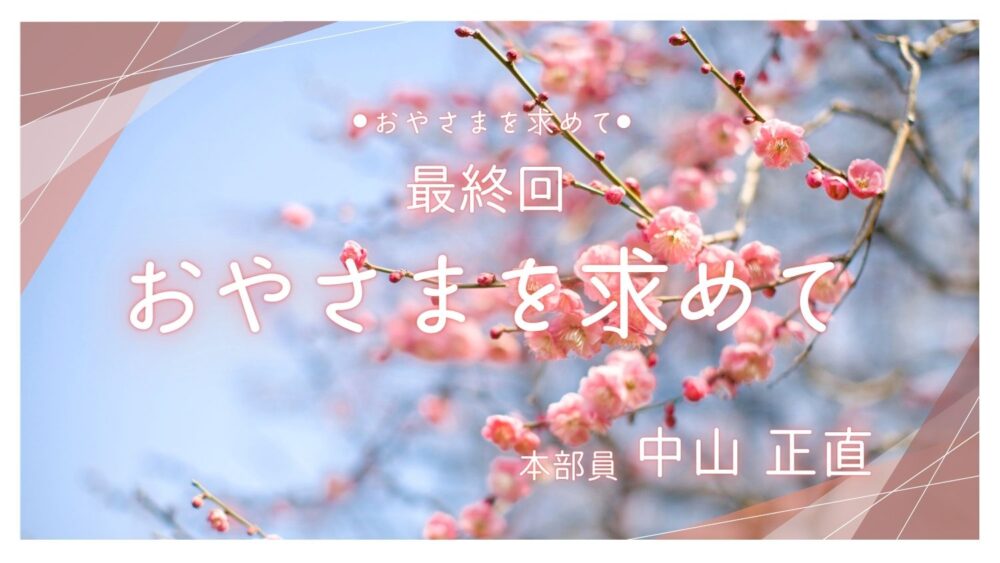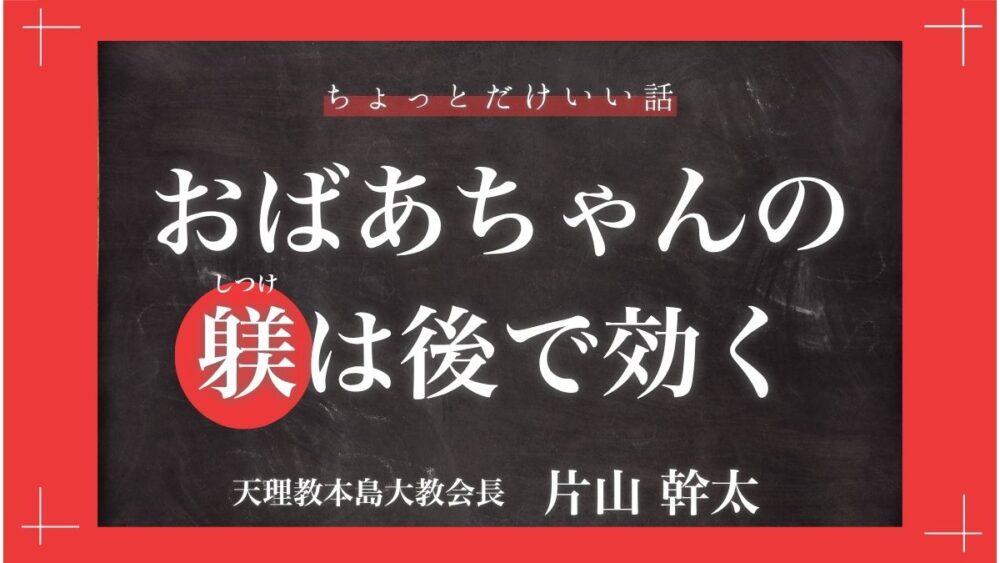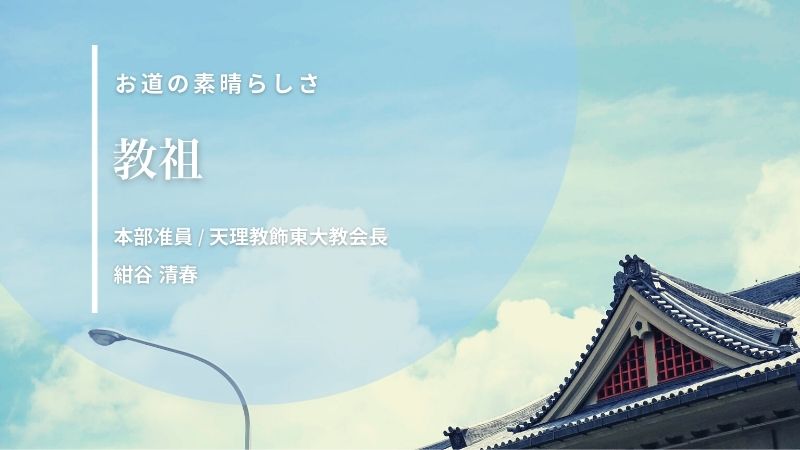教祖について– 関連するページ –
-

第23回「ぢば定め」
01.ぢば定め 明治8(1875)年6月29日(陰暦5月26日)、おやさまは、かんろだいの「ぢば... -
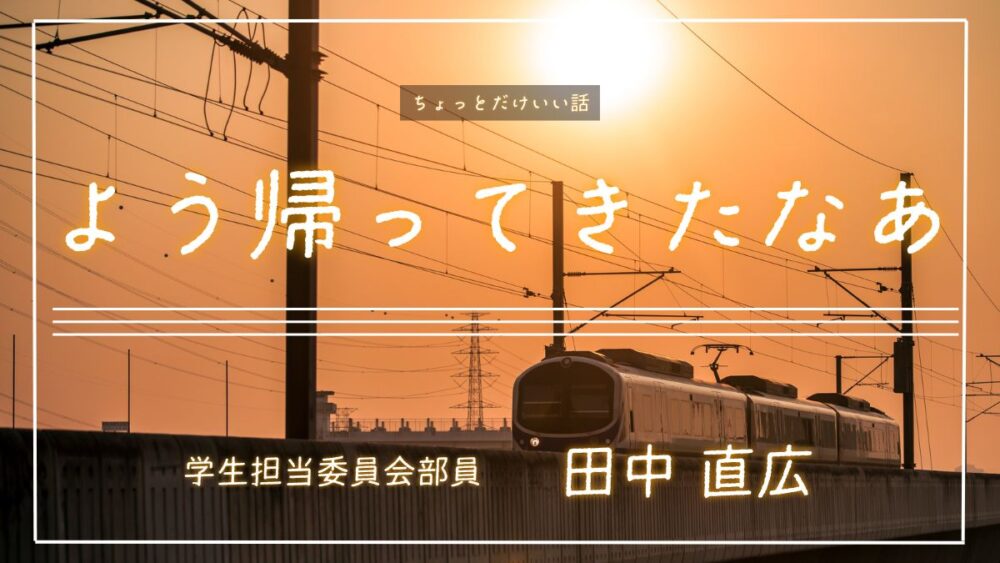
田中直広「よう帰ってきたなあ」
9時間かかる道のり ドラえもんの道具が一つ使えるなら何を使いますか? 私は迷わず... -

第22回「赤衣を召されて」
おやさまは、外に向けて積極的に道をつけにかかられるにあたり、ご自身が月日のや... -

第21回「高山布教②」
01.山村御殿のふし 大和神社での一件の後、おやさまのご存在は、地方庁の役人など... -

第20回「高山布教①」
01.激変する社会 明治の初年、政府は、神道による国民教化を図るため、さまざまな... -

第19回「月日のやしろの理を示して」
断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される -
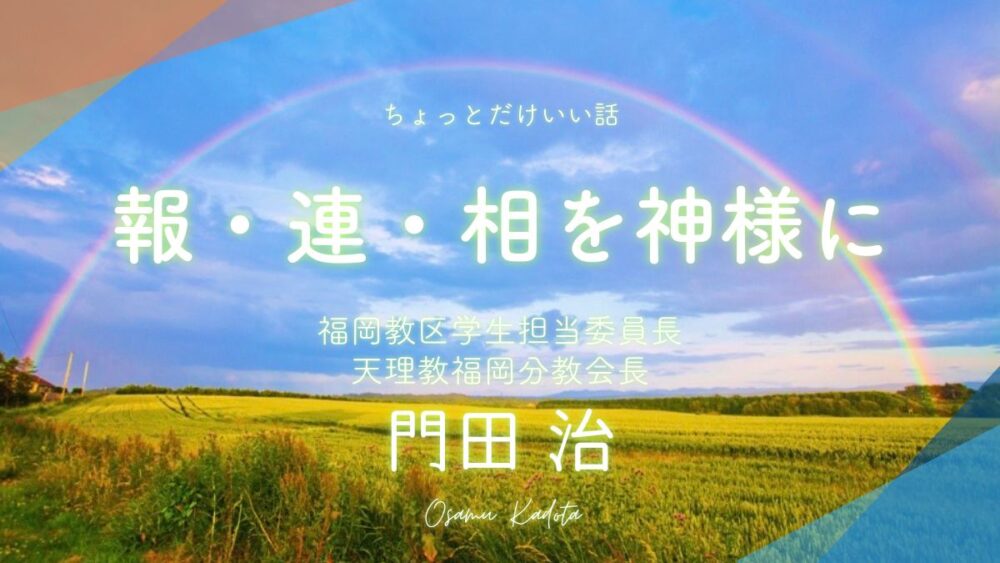
門田治「報・連・相を神様に」
お詫びのおつとめ 26歳で教会長のお許しを戴いて3ヶ月を過ぎた頃でした。「Yさんの... -

第18回「秀司様のご結婚」
明治2(1869)年、おやさまのご長男 秀司様がご結婚なされる -
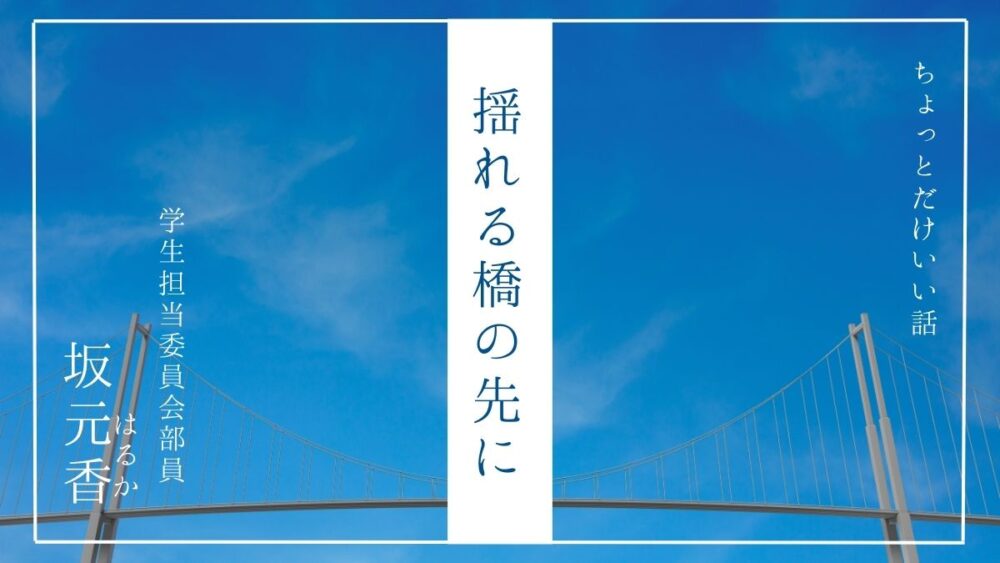
坂元香「揺れる橋の先に」
よう/\こゝまでついてきた 布教の家を卒寮した年のある月に、教会本部の月次祭に... -

第17回「おふでさき ご執筆」
明治2(1869)年の正月より、おやさまは親神様の思召のままに、おふでさきをご執筆なされる -

第16回「つとめ②」
十二下りは、慶応3(1867)年正月より教えられ、続いて満三年かけて、節と手振りを教えられる -
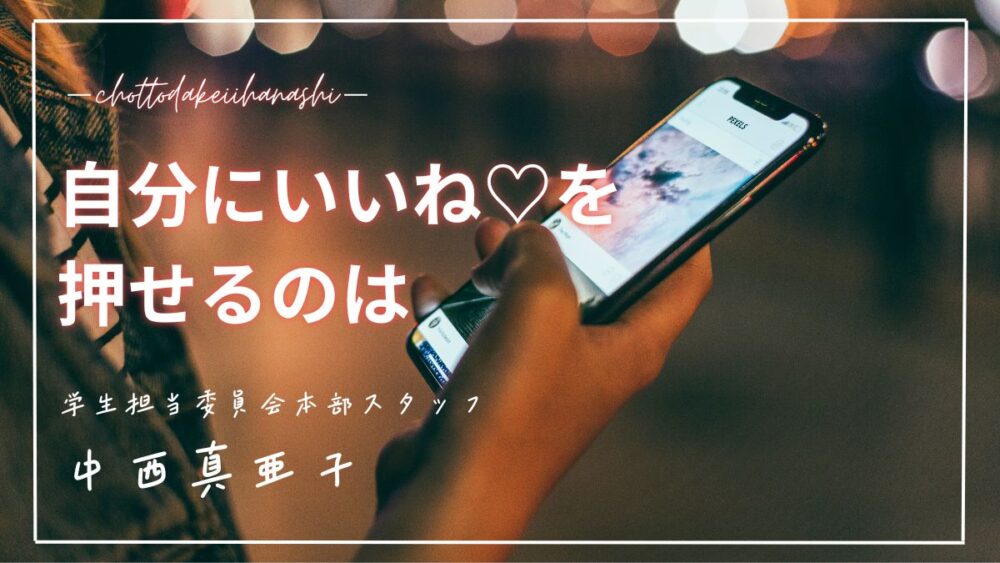
中西真亜子「自分にいいね♡を押せるのは」
その顔が見たくて もしSNSのようにいいねを押せるとしたら、皆さんは自分自身にい...